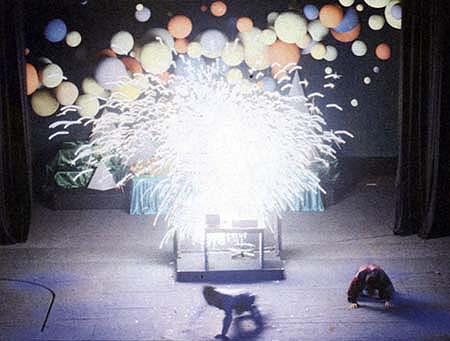|
あの頃、僕は大学の一年生で、そして、自分が一体、何をしたいのか分からないまま、あちこちをうろついていました。
なんとなく入った大学は、まるで養鶏場のような大教室で、教師は、ただ自分の書いた本を読み上げるだけの存在でした。
僕は何度も、大教室の600人全員がいっせいに立ち上がり、人指し指と親指で銃を作り、教師に向かって「ぱんっ」と撃つシーンを想像したものです。僕は、授業に退屈し、合コンに退屈し、マージャンに退屈し、そして日常に退屈しいました。その退屈は、ひりひりとした退屈でした。
困ったのは、自分で自分の退屈の原因が分かっていることでした。それは、一言で言うと「今ある自分と、ありたい自分とのギャップ」という退屈でした。おそらく、ひりひりとした退屈の原因はこれしかないだろうと分かっていました。今ある自分と、ありたい自分との距離が、僕を苦しめている。そして、もっと困ったことに、ありたい自分に関する関心が増せば増すほど、他人とのコミュニケーションが下手になっていきました。今ある自分が語ろうとする言葉の一つにも、ありたい自分が注釈をつけようとするのです。
残念なことに、ありたい自分に関する情報は、いくらでも入ってきました。が、今ある自分に関する情報はとても少なかったのです。
僕は、あの当時、驚くほどたくさんの人と会話しましたが、じつは誰とも会話していませんでした。
 そして、僕は大学二年の時、演劇研究会と言う所に入会しました。いくら体を動かしても、ありたい自分と、今ある自分のギャップを忘れることは、なかなか出来ませんでした。かえって、夢中になろうとすればするほど、そのギャップは鮮やかに僕の前に現れました。ただ「テント洗い」という作業をしている時は、別でした。その当時の公演は、鉄パイプの骨組みに、真っ黒で分厚いビニール・テントをかぶせて、行われていました。公演に使ったテント・シートは、地面いっぱいに拡げると、縦30メートル、横15メートルにもなりました。 そして、僕は大学二年の時、演劇研究会と言う所に入会しました。いくら体を動かしても、ありたい自分と、今ある自分のギャップを忘れることは、なかなか出来ませんでした。かえって、夢中になろうとすればするほど、そのギャップは鮮やかに僕の前に現れました。ただ「テント洗い」という作業をしている時は、別でした。その当時の公演は、鉄パイプの骨組みに、真っ黒で分厚いビニール・テントをかぶせて、行われていました。公演に使ったテント・シートは、地面いっぱいに拡げると、縦30メートル、横15メートルにもなりました。
真夏、青空の下、拡げられたテントに、何本ものホースがいっせいに向けられます。そして、僕達は、弧を描いて落ちた水の柱をくぐり抜けながら、モップを持ってテントの上を端から端まで走るのです。あまりの速度のために、滑って転ぶこともありました。転べば、テントの上は水びたしでどこまでも、滑っていけるような気がしました。仰向けに転び、青空を見上げると、僕には、テントが、青空と同じぐらい大きく
思えたのです。僕は、この作業が大好きで、いつもまにか「テント洗い監督」通称「テンカン」というポジションを獲得していました。そして、ひょんなことから、僕は演出家になり、現在にいたっています。
僕は今でも、時々、大きくなったら何になろうと考えている自分を発見します。変な話ですが、その時は、本気で、大きくなったら何になろうと思っているのです。この前、僕は、大きくなったら果物屋さんになりたいんだと気づきました。もちろん、劇団の借金のことを考えている時は、そんなことは少しも思いませんが、例えば、道を歩いている時、ふと気づくのです。このギャップを埋めるために僕は作家になったんだということは分かっています。でも、書くことでこの距離が埋まるかどうかというのは、また別問題で、書くことで、かえってこの距離が、ひろがることだってあるのです。いえ、書くことで、少なくとも、この距離が、より鮮明に僕の前に現れることは、確実なことです。
突然、果物屋さんになりたい自分を発見するように、突然、過去のワン・シーンがフラッシュ・バックすることがあります。それも、聞こえなかったセリフが、突然、クリアに聞こえてくる瞬間のように、あの時、あの人は本当はこう言ったんだと分かってしまう瞬間のことです。
それは例えば、麻雀なんぞをしている時で、全くもって何の関係もないくせに、突然、過去のワン・シーンが浮かぶのです。そして、長い間、ずっと不思議だったあの人の言葉の意味が、はっきり分かるのです。その時は、どんなに必死に分かろうとしても、全く分からなかったくせに、麻雀をしているまさにその瞬間、いとも簡単にその言葉の気持ちが分かるのです。
 そして、分かった瞬間、その言葉は、僕を引き裂きます。今ある自分と、ありたい自分との距離ばかり見つめていた僕は、あの人の言葉を見つめていなかったという事実が、僕を引き裂くのです。あの人がどれほど臆病で、どれほど逞しくて、どれほど楽しんでいたかという事実が、その言葉に語られていたという事実と、決して気づかなかったあの時の僕に、僕は引き裂かれるのです。 そして、分かった瞬間、その言葉は、僕を引き裂きます。今ある自分と、ありたい自分との距離ばかり見つめていた僕は、あの人の言葉を見つめていなかったという事実が、僕を引き裂くのです。あの人がどれほど臆病で、どれほど逞しくて、どれほど楽しんでいたかという事実が、その言葉に語られていたという事実と、決して気づかなかったあの時の僕に、僕は引き裂かれるのです。
そして僕は、引き裂かれたまま、麻雀を続けます。勝ったり負けたりしながら、麻雀を続けます。勝った奴が、朝のアスファルトを歩きながら、あくびひとつ加えて、「またやろうぜ」と言います。負けた奴が、元気いっぱいに「もう一生、しないぞ」と言います。
そして僕は、うんうんとうなずいて、歩き続けるのです。
今日はどうもありがとう。ごゆっくりごらん下さい。では。
(ピルグリム・ごあいさつ1989. 9 鴻上尚史)
|
![]()
![]()